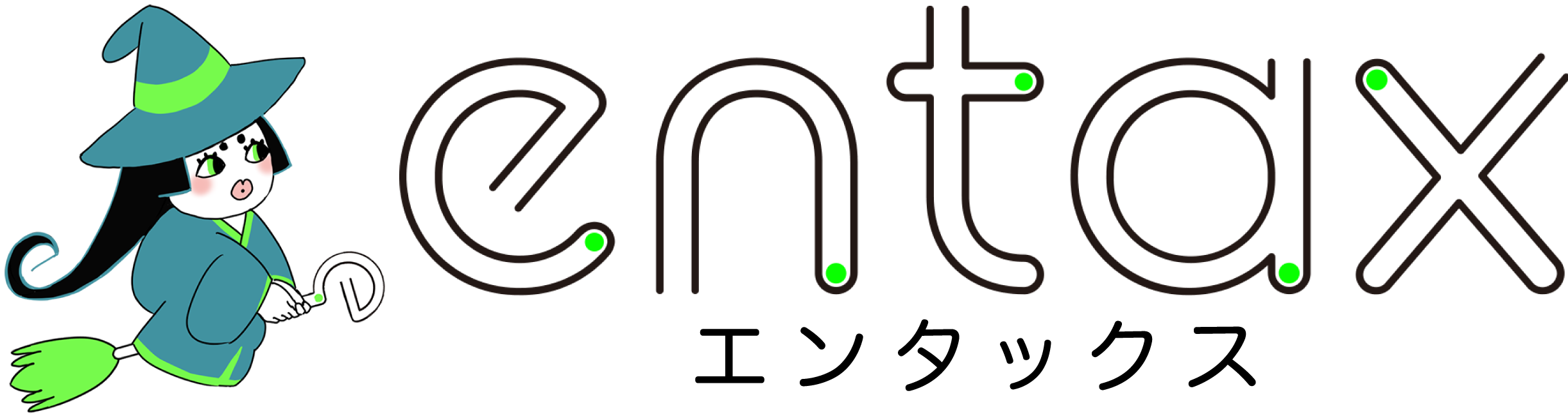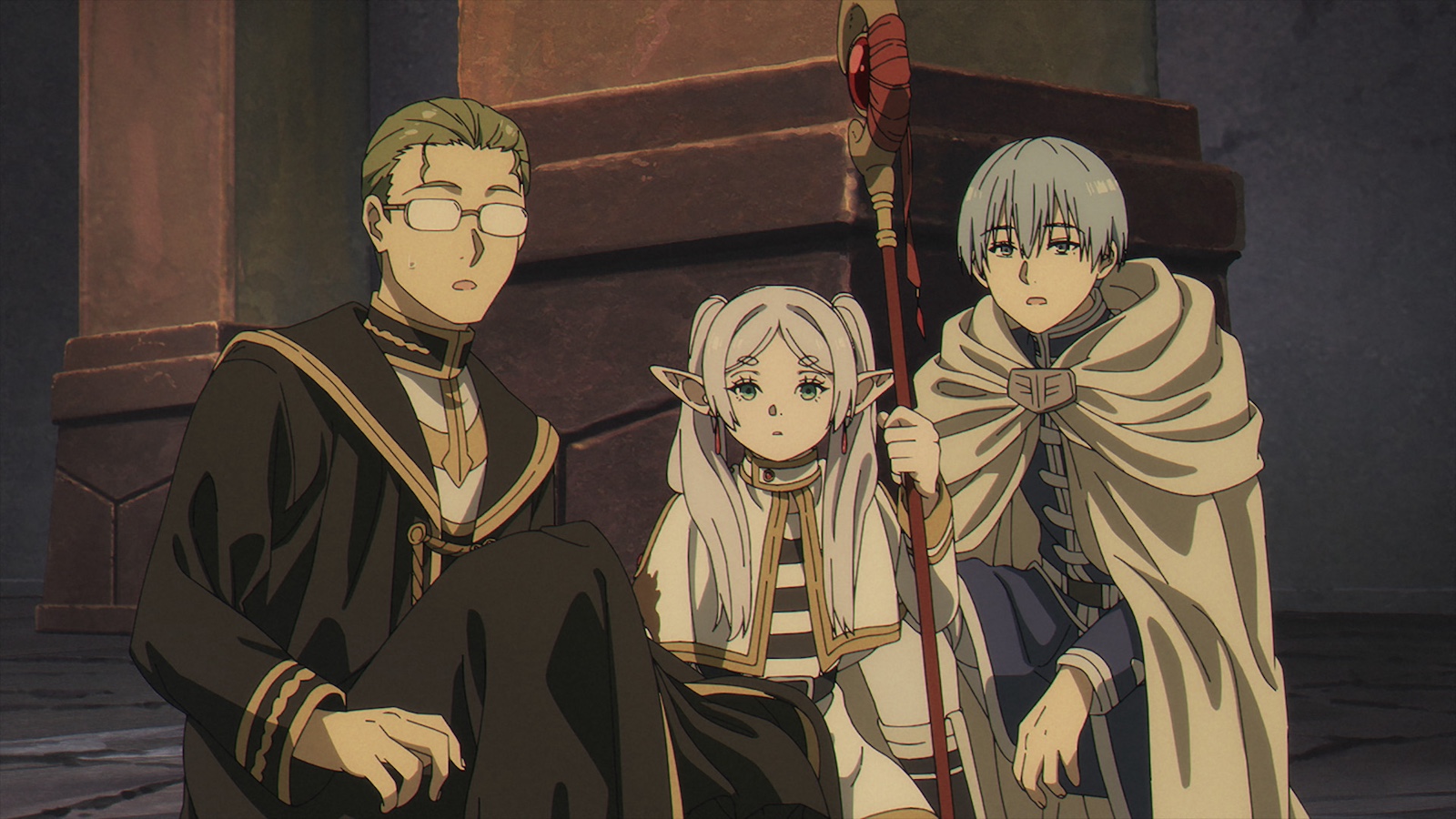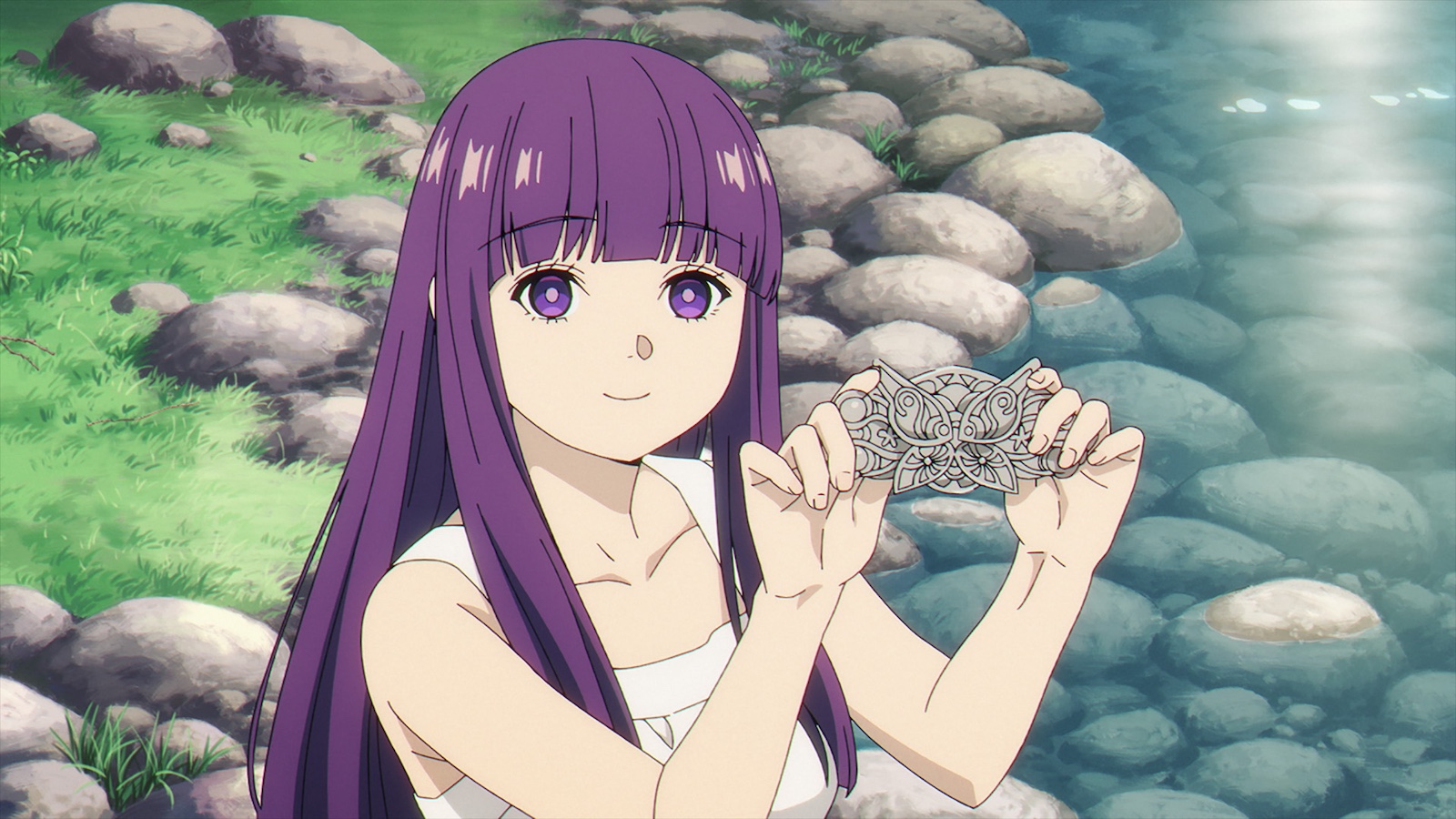出川哲朗「何がヤバいんだ?と思ってた」が実はヤバかった…オーバーツーリズムの影響で人気観光地で起きている現実とは

出川哲朗と伊沢拓司がMCを務める特番『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』が読売テレビ・日本テレビ系全国ネットにて、9月25日に放送された。さまざまな場面で「ヤバい!」と叫ばれる今の日本は、一体どれほどヤバいのか?はたまた意外とヤバくないのか?この番組では、さまざまなデータから日本が抱える問題のヤバさを紐(ひも)解き、番組独自の【深掘り調査】でその本質に迫っていく。
テーマは『ニッポン、オーバーツーリズムが深刻すぎてヤバいよ!?』。日本全体の外国人観光客数は、2014年は1341万人だったが、昨年、その数は3687万人まで増加。この10年間で3倍近くに膨れ上がっている(出典:日本政府観光<JNTO>)。京都市の外国人宿泊者数を見てみると、10年前は約183万人だったのに対し、昨年は約821万人と448%も増加しており(出典:京都市観光総合調査)、現在、京都は外国人観光客であふれかえっている。
そんな京都では今、異常な物価高になっているという。京都の多くのホテルが、外国人観光客のお財布に合わせ値上げを敢行。京都市内の主要ホテル平均客室単価は、1年で17.2%も値上がりし約3万640円と、過去最高を記録した(出典:京都市観光協会データ月報<2025年4月>)。京都旅行といえば、日本人の定番の旅先であったが、物の値段が高い京都中心部の人気観光地では日本人観光客が減少。一方で郊外の観光地では日本人観光客は増加しており、“隠れ観光地”に避難する傾向が見られる(出典:京都市産業観光局(MICE))。
中心部で老舗店を運営する方々に話を聞くと、日本人観光客が減少していることについて「寂しい」としながらも、「そんなことは言ってられない状況」「それも日本の現実」と受け止めざるを得ない状況のよう。また、「(外国人が好む食事に変わってしまい)育まれた食文化はなくなってしまう」と、インバウンドマネーがもたらす繁栄と昔ながらの日本文化の継承、その天秤(てんびん)に揺れているようだ。

ところ変わって、京都と同じく人気観光地、神奈川県の鎌倉市では深刻な交通渋滞に悩まされていた。平日なら車で12分の道のりが、週末は約4倍の47分もかかるのだとか。一刻を争う緊急車両も遅れかねない事態に、鎌倉市は渋滞緩和のため一部の道路を有料制にする対策を検討しているが、まだ実施には至っていないという。
また北海道の富良野市は、人口約1万9000人に対して外国人観光客は年間約14万8000人と、10年前に比べ284%増加(出典:富良野市)。さらには、外国人に高値で土地が売れるので、家を売却して引っ越してしまう人が続出。購入した外国人は、主にスキーシーズンの冬に訪れるため、夏はゴーストタウンのように閑散としてしまうという。しかし、古くから暮らす住民の中には「働くところがないから若者がいなくなる。外国人に来てもらって観光産業を優先しなかったら、過疎化でどうにもならない」という声も上がっていた。

「現状を見ていくとデータと違ったところもあるし、データで見るとまた現状と違ったところもあるしで、非常に多角的に考えなきゃいけない問題だと思うんですけど」と伊沢。「正直最初は、外国の方が増えてくれて、ホテルもいっぱいになって、コロナの時皆さんホテル経営とか大変だったから、本当助かって、何がヤバいんだ?良いことしかないじゃないかって思ってたんだけど、V(VTR)見てたら結構ヤバいですね」と問題の深刻さを感じる出川。

2030年に外国人旅行者の数を6000万人に増やすという目標を掲げている日本政府。ゲストの石田健は「それを目指すんだったら、さすがにやっぱりもっと分散させようとか、そういうことにやっぱり国は力入れてほしいな」と、ビザを緩和した一方で、その先のトラブルを見据えず、これまでに受け入れ体制が整えられなかった現状に懸念を口にした。
出川は日本のオーバーツーリズムが、どれぐらいヤバいか総括を促されると、答えは『大ヤバいよ』。「これ最初はもう“小ヤバいよ”でいいだろと思ったんですけど、このVを見て、これはとてもじゃない、“大ヤバいよ”ですね」と理由を説明。そして「ヤバいよと言うけど、嫌なことばっかりでもないし、ちゃんと対策しないとねって話ですよね」という伊沢の言葉に共感した。

番組の最後、「こんな形でニュースを語るのは僕すごい大事だと思っていて、難しい問題は真面目なことを言わなきゃいけないんだって、皆さん思い込んでますけど、実はこんな感じでポップに語るのは大事」「意外にやっぱこの番組は高貴なんじゃないかな?」と語る石田。すると出川は、「俺なんか途中でこうやってチラチラ見ちゃうんですよ、モニターを。そしたらうなずいてる俺カッコイイなって」と、ニュースを語っている自分に見惚(みと)れていることを明かし、スタジオは笑いに包まれた。