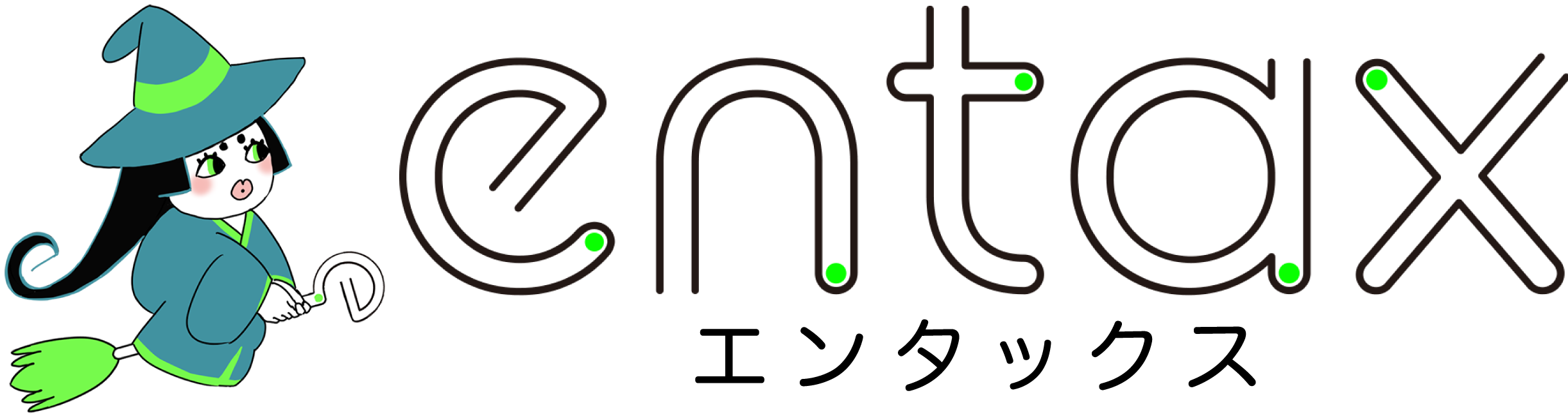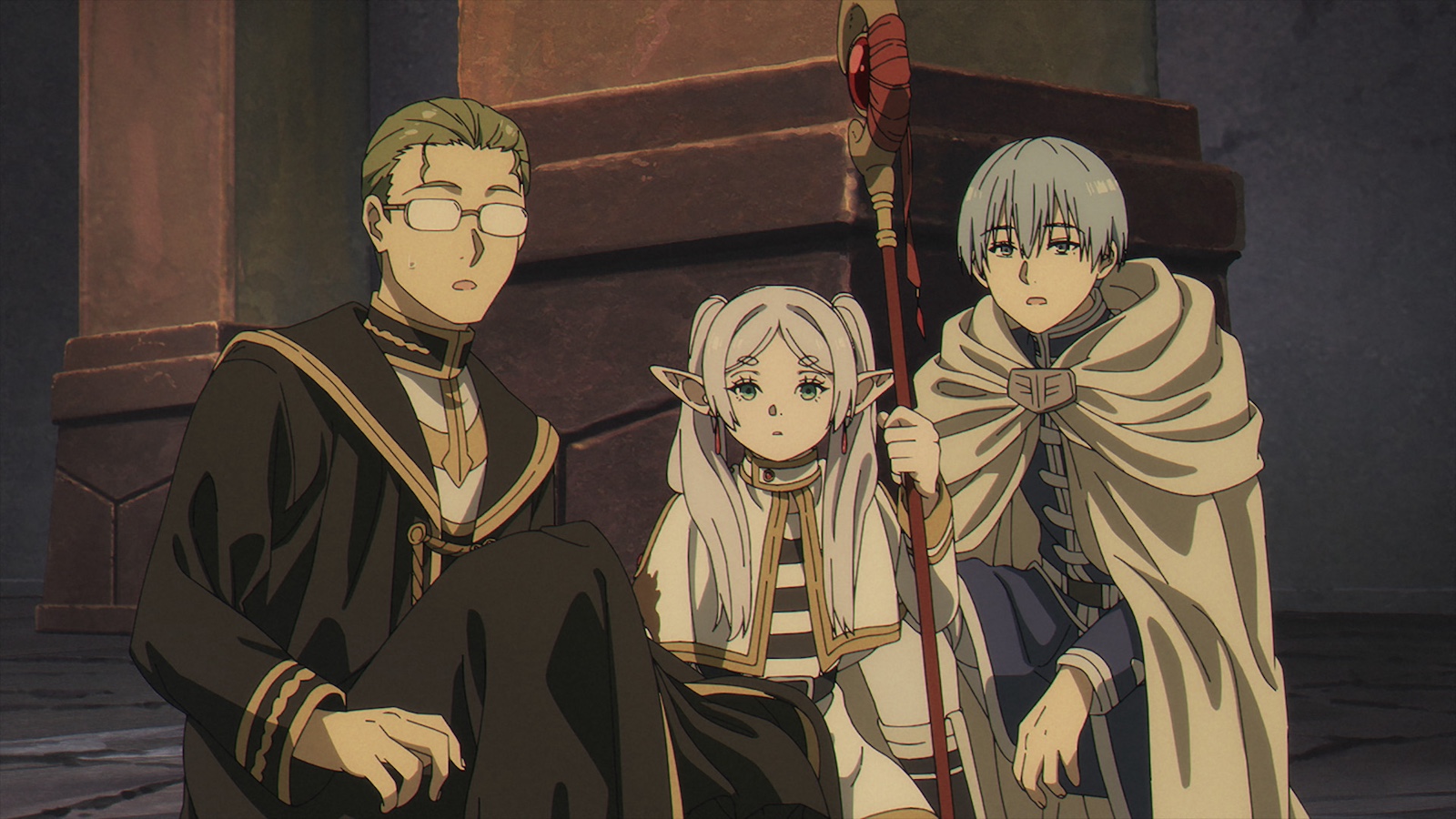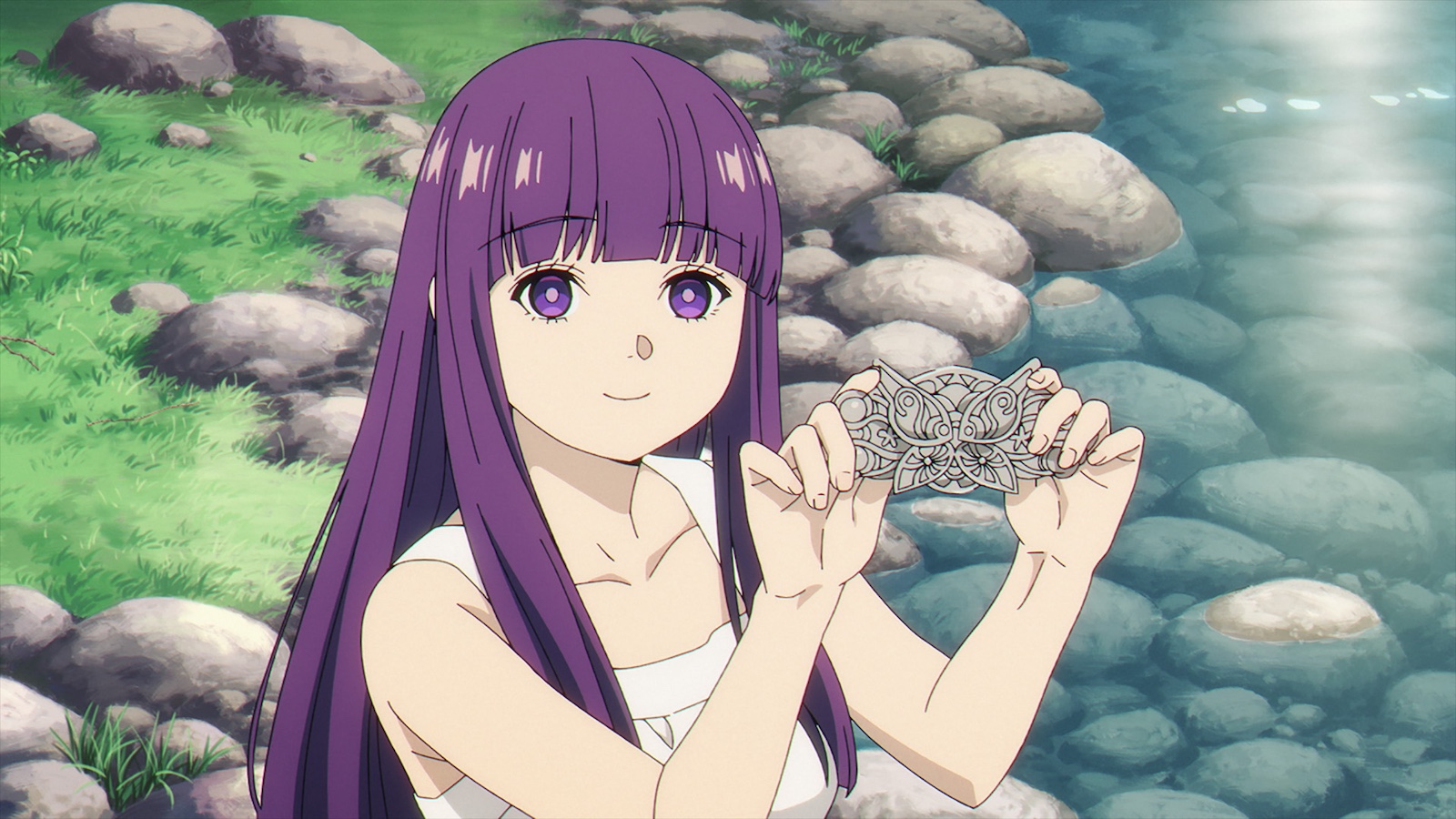カズレーザー 孤立集落はなくすべき?安全性と文化保全の間で揺れる議論…令和時代に必要な地方の姿とは

カズレーザーがMCを務める『カズレーザーと学ぶ。』が19日に放送された。今回は『芸能人が提言 令和の新法律SP』というテーマ。普段は講義を聞く側である出演者たちが、現代社会の問題を解決するべくオリジナルの法案を持ち寄り議論した。シソンヌ・長谷川忍は、『災害が起きた時に危ないので、町から離れて暮らす孤立住宅をなくす法』を提案。近年問題が表面化している日本のインフラ老朽化問題に切り込んだ。
人手が減少し経済も停滞しているなかで、インフラの維持費や修繕費は増すばかりだといい、現実に昨年発生した能登半島地震では道路などのインフラが遮断され、山間部の集落が孤立。電気や水道が2週間近く途絶えた。人口の極端に少ない地域はインフラの整備にもお金がかかり、災害時には危険として、長谷川は引っ越し費用を負担することで孤立住宅をなくす法案を提案した。

長谷川の提案に対して、スタジオの意見は真っ二つに割れた。賛成派としてACEesの浮所飛貴から「人口密度が少ないところにインフラ整備にお金をかけてしまうんだったら、国としてもっといいところにお金を使える」などの意見が出る一方、反対派としては自身の故郷に廃村になった地域があるというオカリナから「宮崎県の西都(さいと)市ってとこ出身なんですけど、元々あった村に行ったことあるんですよ。人が住んでた家が朽ち果ててた」と、一度なくなった地元が戻ってくることのない現実が語られた。
賛成4人、反対3人と拮抗(きっこう)する中で、神戸大学大学院工学科教授の小池淳司氏は「一般に政府が支出しているインフラの経費は年間20兆円越え」と、インフラにかかる支出は政府予算の約5分の1を占めると解説。上下水道や道路の耐用年数が約50年であるというが、現在のインフラのほとんどは、高度経済成長期に整備されたもの。点検しながら使っているが、予算の上限があるため、維持や修繕に限界が見え始めているという。「整備すること自体は難しくない」と小池氏はいうが、1980年代以降、事業者と政府の癒着が問題視され、土木事業へのバッシングが高まったことが、問題を複雑化させているのだという。

小池氏はさらに、生まれ育った土地への愛着や文化の保存も、長谷川の法案を実施するうえでの懸念と話す。地方都市の効率化は都市住民にとっては節税になるが、町ごとの文化や風土の消失につながり、それらは一度なくなれば戻らないと訴える。加えて「地方が衰退していくという前提でお話をされている」とも話し、イギリスやフランスの例を紹介。両国では農業や製造業の軸を地方に移して再生しようとしており、これはイギリスやフランスが、コストの問題以前に環境の保全や国防の観点から、地方に人が住み続けることのメリットを重視しているためだという。

また明治大学政治経済学部教授・野澤千絵氏は、人口減少への対策として期待される『コンパクトシティ』という都市モデルについて解説。居住エリアをあらかじめ決められた拠点エリアに集約し、人口密度をキープ。病院や学校などを含む行政サービスを維持し、スーパーマーケットや病院など民間の施設の撤退も防ぐ都市政策であるとのこと。2014年度から国の政策として制度化され、およそ600の都市で取り組みが進められているという。
説明をうけ、再び出演者たちの意見を募ると、カズレーザー以外が全員反対にまわるという結果に。反対から賛成となったSHELLYからは「選択肢があった方がいいなって。(ほかの土地へ)動く資金は出します、それでもそこがいいです、という人たちのためにじゃあどういう風にインフラを整備して、上手に選択肢を守ってあげる、というのが社会としていい」や、浮所からも「孤立している場所にも、消したくない日本の良さがある」といった意見が出た。

ただ1人、賛成派として残ったカズレーザーはというと、「都市部で仕事してるっていうのは結局、東京一極集中を良しとしているっていう呪縛から逃れられないので、その責任は(賛成といって)取るべき」とコメントして締めくくった。
【TVer】最新話を無料配信中!
【Hulu】最新〜過去話配信中!